問い欠ける物語
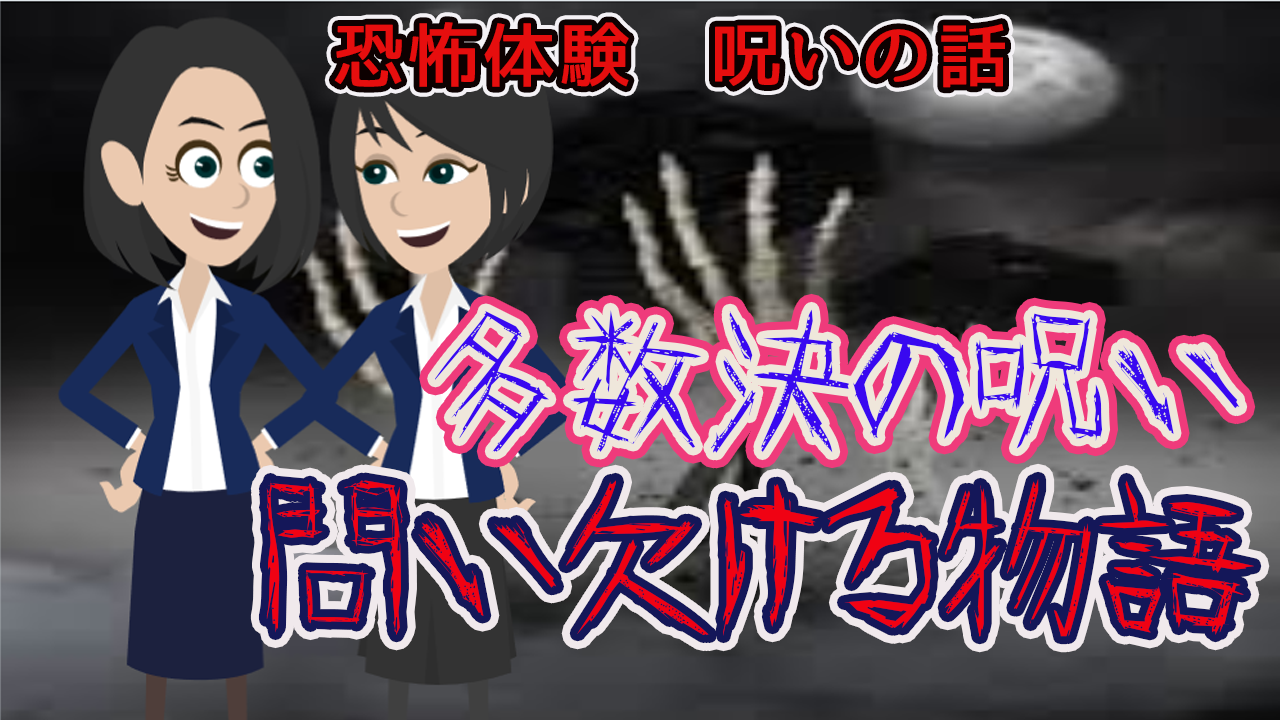
中学二年生のとき、千歳は私のクラスに転校してきた。 おとなしくて、おどおどしていて、いつも何かに怯えている消極的な女の子。 転校初日の挨拶のときなんて緊張で「あの、えっと……」しか言えなくてみんなで笑っていた。馬鹿にしたわけではなくて、その小動物のようなかわいらしさが印象的だった。 どうしてみんなが笑っているのかわからない千歳は、ぽかぽかとした雰囲気に包まれて思わず小さく笑みをこぼした。左手を口元に添えて目を細めたあと、生徒達の興味が自分に向いていることに気付いた千歳は顔を真っ赤にする。 窓から差し込むやわらかな光と、千歳の笑顔がとても、とても印象的だった。
千歳は両親の都合で東京から引っ越してきたらしい。休み時間に生徒達が押し合いへし合いで千歳を質問攻めにしていたからなんとなく聞こえてきた。コンビニもないような片田舎に住んでいる私達にとって、東京の暮らしはただただ羨望の眼差しである。 東京は夜になっても眠らない街であること。おしゃれな洋服屋で溢れていること。モデルのスカウトマンによく声をかけられたこと。質問に答えているときの千歳は不慣れながらも、自分と接してくれる同級生達に心を開いていった。
でも、中学生というのはとても短絡的で、いっそ清々しいほど残酷である。 聞かれたから丁寧に答えただけ。つまらない子だと思われないように必死に答えただけ。 なのに東京の話をする千歳に対して、同級生達は嫉妬の目を向け始めて、次第には無視をするようになった。「田舎育ちの私達は見下している」とか「心の底では笑っている」とか。 千歳にはありもしない感情が教室中に蔓延していた。
私にもどこか疎ましく思っている部分はあった。けれどそれ以上に転校初日のあの笑顔が、東京の暮らしを知るあの経験が、刺々しくて窮屈な気持ちよりも千歳と一緒にいたいという気持ちの方が強く高まっていた。
「『透明』って色がある以上、人は本当の意味では孤独になれないのかもね」 読書家の千歳はいつも難しい言葉を使う。
「孤独になれないのは良いことなんじゃないの?」
「でもそれってずっと多数派でいないと駄目じゃない」
あいかわらず千歳の考えることは理解できない。 孤独になれないことも、多数派でいることも、それの何が悪いというのだろう。 だけど、少数派でいるということはそれだけ味方も選択肢も少ないということである。 千歳の机に花瓶が置かれていても、教科書の中におもちゃのゴキブリが仕掛けられていても。 下駄箱から靴が消えていても、一人で日直当番をこなすことになっても。 私以外で千歳に寄り添う人は誰もいなかった。
ある日、放課後の教室で静かに泣いていた千歳を見てしまう。 大切にしていた本がカッターでボロボロにされていたのだ。 自分にはどれだけ嫌なことをされても我慢していた千歳が、本を傷付けられて涙を流している。感情の優先度というのか、感じるべき情緒というのか、そういったものがちぐはぐに思えて、そこで初めて同級生達に対して沸々とした怒りがわいてくる。 自分自身でも得体の知れない感情に整理が付かないまま家へと向かっていると、 「……あれ?」 空き地だったはずの場所にいつのまにか駄菓子屋が立っていた。 看板には『呪い代行日本呪術研究呪鬼会』と書かれている。
一刻も早く立ち去りたいのに、足は勝手にお店の中へと進んでしまう。
「いらっしゃい」 急に声をかけられて肩を震わす。襖の奥から狐のお面を被った女性が出てきた。
「私は雫。呪い代行日本呪術研究呪鬼会の一員よ」
「呪い代行?呪鬼会?」 聞いたことのない名前に戸惑っていると、手振りだけで座布団に座ることを促される。
おずおずとしながらも女性から目を離さずに座った。
「代わりに呪いをかけてくれる、ってことですか?」
「それは呪いの内容にもよるわね」 雫さんと名乗る女性が人差し指、中指、薬指の三本を立てる。
「一つ、依頼者の代わりに呪いを実行する。二つ、依頼者が呪いの概念を体現する。三つ、呪いを物に肩代わりさせる。一口に代行と言ってもその性質は様々なのよ」
私には難しい話で頷くことさえもためらわれた。戸惑っているのを察したのか、雫さんが「まぁ、少しずつ『呪い』に関して擦り合わせていきましょう」とほほえむ。
「はぁ……」
「あなたは呪いに対してどんなイメージがあるかしら」
「呪い。ですか?」 言われて、しばらく考え込む。
「それは、ひとりかくれんぼとか?」
ちょっと前に動画で見た覚えがある。人形に自分の爪を入れるとかそんなだった気がした。
「それもそうね。三つ目『呪いを物に肩代わりさせる』方法」
「他にもあるんですか?」 あとは丑の刻参り……とか?
「例えば、悪口。あれも一種の『呪い』で、呪い代行でもあるわ」
「悪口……」
「概念の話よ。感じ取るものだから無理に理解しなくていいからね」 理解しようとしなくても頭が混乱してくる。数学の問題より大変かもしれない。
「それで、あなたはどういった悩みを持っているの?」
「悩みですか?」 給食の量が多いこと。宿題がむずかしいこと。お気に入りの傘が壊れてしまったこと。 中学生なんてまだまだ子どもだなんて言われるけど、子どもには子どもなりの大きな問題や困難がつきまとう。
でもやっぱり、千歳のことが思い浮かんで少しだけ涙が出そうになる。 ふと、雫さんが私の頭をやさしくなでてくれた。
「思い出させてごめんなさい。そう、お友達のことで悩んでいるのね」
「え?」 まだ何も話していないのにどうしてわかったんだろう。
「私が『呪い』を代行してもいいのだけれど。そうね――」 雫さんが私の目をジッと捉える。なぜだか鷹に睨まれた小鳥のように萎縮してしまう。
「あなた自身が制裁を加えたいなら、あなたが呪いを代行すればいい」
「『呪い』って、そんな……。たまたまここに迷い込んだだけですし……」
あら、と雫さんが両手の人差し指でバツを作る。
「『迷い込んだ』じゃなくて『導かれた』のよ。ここは『呪い』に関わる人しか来れないもの」
「え、私ってもう呪われてるんですか?」
「その場合もあるけれど、今回はあなたが『呪い』を代行できる立場にいる、ということね」
代行。私が、誰かに罪と罰を与える。 千歳の悲しい顔が頭をかすめた。同級生達のにたにたとした表情が頭にこびりついた。 私が、千歳のために、同級生達に『呪い』を代行する。 雫さんの顔を見つめると、私に向かってこくんと頷く。
「大勢の人を呪うにはそれなりに大きな代償が必要なのよね」 うーん。と、人差し指でくちびるを撫でる姿が大人っぽいなと思った。
「そうね。あなたには『多数欠』の『呪い』をかけてあげる」
「多数決?」 って、あの少数派を見せしめにする多数派のことなのか。
「『多数派が欠ける』と書いて『多数欠』」
「それが呪い、……ですか?」 もっと人が不幸になるとか、不吉なことが起こるとかを考えていたから戸惑う。
「あなたが議題を呈する。そして問われた人達が賛否を決める。多数派になった人達は議題に関する記憶が文字通り『欠けて』しまう。それが『多数欠』の『呪い』よ」
「はぁ」 その『呪い』で迎える顛末を想像できなくて気の抜けた返事になってしまう。
「例えば『千歳ちゃんがいじめを受けていると思う人』と問いを投げ掛ける。きっと、クラスの子達は全員手を上げると思うわ。そうしたら、千歳ちゃんが『いじめを受けている』という記憶が全員から欠ける。結果、クラスからいじめはなくなる。それが『多数欠』の呪いよ」 なるほど。と、心の中では納得しつつどこか淀みや引っかかりを感じる。
「でも、お金ないです」
「いいのいいの。呪いを求めている人達に呪いを提供する。それが私達の『呪い』だから」
雫さんの言っていることはよくわからなかったけど、なんとなく頷くことにした。
「あーそれとね、さっき大きな代償が必要と言ったけど」 やっぱりお金を取られるのかなと思って身構えてしまう。
「呪いの代償はあなたが『少数派で居続けること』よ」 この先、生きている限りね。と、雫さんがほほえんだ。
朝のホームルームで先生が一人の女子生徒を呼び出した。
「穂摘さんの給食費が盗まれました。今から話し合いを始めるのでイスを丸くしてください」 隣に立たされた生徒、穂摘が「めんどくさ」と言いながら一部の生徒にピースサインを送る。けたけたと笑い合う姿と、あの手振りが気になりつつも机を教室のすみっこに寄せた。
「奥沢さん、真ん中に立ってください」
「え?」 脈絡もなく千歳の名前が呼ばれて二人で驚く。 おずおずとしながらも席の中心へと歩いていく千歳を見つめる。
にやにやする生徒、あくびをしている生徒、めんどくさそうな生徒。
『では、多数決をします。奥沢さんが給食費を盗んだと思う人』 正義感に支配された先生が冷たく問いただす。 ……そうか。穂摘が自分で「給食費がなくなった」と嘘をついて、取り巻き達と画策しては千歳を犯人に仕立て上げようとしているのだ。 先生の歪んだ正義感を利用して千歳をクラスの見世物にする。
誰かに操られたように生徒達の手が次々と上がった。
「奥沢さん。どうして穂摘さんの給食費を盗んだんですか?」 クラス中から「信じられなーい」とか「穂摘さんかわいそう」といった乾いた声が飛び交う。 千歳の目が真っ赤に充血して涙がじんわりとたまる。 唇からは血が滲んでいた。嗚咽を出さないように。千歳なりのせめてもの反抗だった。
ふざけるな。声を上げようとしたその瞬間、 「あれ、今、何の時間なの?」 ……は? 先生にふざけている様子はなく、穂摘もどうして自分が横に立っているのか理解できていない顔だった。ざわざわと教室中がざわめく。私と千歳で顔を見合わせていると、あっと気付く。
『あなたが議題を呈する。そして問われた人達が賛否を決める。多数派になった人達は議題に関する記憶が文字通り『欠けて』しまう。それが『多数欠』の『呪い』よ』 雫さんの言葉が頭の中を駆け巡る。同級生達の記憶から給食費の件が欠けたから。 唯一、手を上げていない私と千歳だけが記憶を保っている。 これが『多数欠』の意味。
……だったら、今なら。 立ち上がる。輪の中心にいる千歳の左手を繋ぐ。繋いだ。 息を吸って、吐いて。
「千歳がこのクラスに不必要だと思う人」 何が起きているのかさっぱりわからない同級生達と先生が互いに顔を見合わせる。 その一人一人の顔を睨んだ。 穂摘がおずおずと手を上げるのを合図に、同級生達もゆっくりと手を上げる。 これで全員の頭から千歳に関する不条理が欠けるはずだ。 嬉しくなって横を振り向く。
「……え」 右手を上げている、千歳が、なんで。……どうして。 千歳が振り向く。泣きながら、ほほえんでいた。 「ありがとね」 そう言って笑った千歳は、いつのまにか私達の存在から欠けていった。 布団の中で目を覚ますと、いつの間にか涙が流れていた。
千歳が欠けてから十年余りが経った。 あのとき、千歳が笑って、そして自ら手を上げた理由は今でもわからない。 大きくなるにつれて、否が応でも私達にはいくつかの分岐点が訪れる。 進学、就職、結婚、葬式。 その全てで最善の道を選び続けるのは困難で、ときには選択を間違ってしまうこともある。 答えは誰かが指し示してくれるものではない。 多数派が不正解なこともあるし、少数派が正しいときもある。
「呪いの代償はあなたが『少数派で居続けること』よ」 雫さんの言う通り、それは呪いの代償であった。 人と違うことをすると目立つ。おかしいと言われる。変わってると煙たがられる。 それでも個性や身分、考え方や倫理観を押し殺してでも私は少数派でいないとならない。 大学時代、卒業旅行でテーマパークに行くか、観光地に行くか多数決が行われたとき私はこわかった。どちらを選んでも選ばなくても、場所そのものが欠けてしまうんじゃないかって。
社会人の今、上司から「お前は人と合わせるということができない」と何度も怒鳴られた。 作って、偽って、取り繕って。本当の私はもうどこにもいなかった。 人を呪った以上、呪った者は『人』と呼べなくなる。それはもう、醜い『何か』だ。 もう、生きることの何もかもに塞ぎ込む。
ふと思い立つ。自分で『私がこの世にいなくてもいいと思う人』と聞いて、私自身が手を上げる。そうすると私はどうなるのだろうか。私が欠けて、消えてしまうのだろうか。 だったら、それでもいいのかもしれない。一人の場合は多数派になるのか少数派になるのか。「私がこの世にいなくてもいいと思う人」 手を上げる。上げた。私が――
※この作品はフィクションです。実在の人物・団体・事件とは一切関係がありません。



