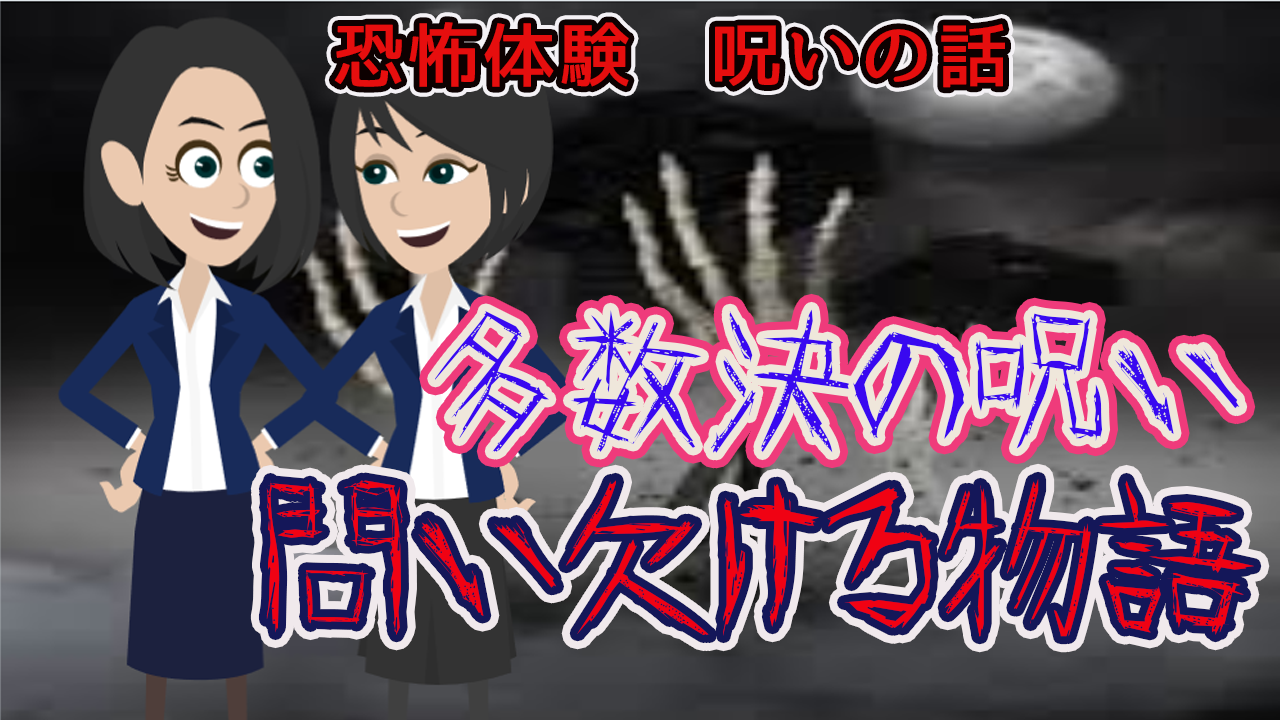呪いの黒箱

あなたは呪い代行という商売をご存知だろうか。 ネットで「呪い代行」と入力して検索すれば、代行者をいくつか探すことができる。 私もその呪い代行を生業とする日本呪術研究呪鬼会の呪術師の一人だ。 だが、その検索ではどう探しても、私の名前は出てこない。あくまでも表向きは占い師だから。 その占い相談の中で「どうしても恨みを晴らしたい」というような依頼があれば、初めて裏の顔を見せる。
実はこの裏のほうが私の本業なのだが。といっても、この手の依頼は、看板にしていないせいか、ほとんどない。 私の占いには占星術やタロットなどは必要ないし知識もない。というのは、相手の顔、特に額を注視するだけで、その人が考えていることが多少なりとも読み取れるからだ。一種の読心術といったところか。 考えていることがわかるから、そのことを伝えるだけで「すごい!なんでそれがわかるのですか?」と誰もが驚く。そして客の間で「あの占い師の占いはよく当たる」となる。 そうやって、今までなんとか大きな問題を抱えることもなくうまくこなしている。そう、あの客が現れるまでは…。
その客は、今夜はそろそろ店じまいしようかというタイミングでやってきた。 五十過ぎの男性。サラリーマンだ。生ける屍のような顔をして現れた。安物の背広にくたびれた靴。悩みは十歳も年下の上司によるパワハラ。お前はクズだ、給料ドロボーだ、無能。死んじまえ、とさんざんに罵倒され、憔悴しきっていた。 私はその客の額をじっと眺めた。すると、とてつもない邪気が漂っているのが見えた。敵意は上司に向けられている。そうか、パワハラで悩んでいるのか…。占いでは一般的に未来予測をしつつ、何か前向きな暗示を添えてあげて気を遣ってあげるルールなのだが、この客には前向きな暗示を与える要素がなにひとつなかったのだ。 その客がいまどのようなことを考えているかおおよそのことは見当がついたものの、私がどう話を切り出せばよいか迷っているとき、客がふいにつぶやいた。
「先生って、呪い代行もしてくださるんですよね?」
「どうして、それを?」と問い返すと、ここでお世話になった同僚からたまたま聞いたとのことで、そのときに呪い代行の話も知ったということだった。 ここに来た目的は占いよりも、呪い代行だったのか…。 私が客の名刺を受け取ると、ここを紹介した同僚のこともはっきりと思い出した。その同僚とは占いをしてあげたことがきっかけになり、妙に気が合って一緒に飲む機会も増え、世間話をしていくうちに呪いの話になり、相談を持ち掛けられるようになったのだ。
私が「あなたをここまで追い詰めてしまった上司に対して呪いの代行してほしいということなんですね。」と聞いた。客は静かに頷いた。そうか、呪い代行の怖さを知っているなら仕方がない。
「…わかりました。では、呪い代行をいたしましょう。ですが、この代行はこの一回限りにしてください。現実的にもその方が…」と私が言うと、客は「わかりました。」と答えたので引き受けることにした。
呪いをかけるということは、呪う強さの分だけ己の命を縮めることにつながるからだ。多用はよくない。 私はまず、相手にどんな呪いをかけたいのかを確かめた。客は相手に懲らしめる意味合いで「痛い目」に遭わせるだけでいいと答えた。 続いて私は、客に呪う相手の毛髪を用意するようにお願いした。毛髪は毛根がついたものに限る。その毛根内のDNAを使って依頼主の念を本体のDNAに送り込むことがポイントだ。
「毛根のついた毛髪、持ってこられますか?」
「必ずお持ちします」 こうして、その日の鑑定は終了した。 その三日後。客はこちらが指定したものを持ってきた。差し出されたハンカチを開くと、そこに毛髪が一本。確かに毛根もついている。
「ずいぶん早く用意できましたね。」
「ええ、まあ、なんとか。」
「わかりました。お預かりします。」 どうやってこの毛髪を手に入れたのかは聞かないことにしている。相手の名前も素性も聞く必要はない。そのことには関心がないし。私の仕事には無縁だからだ。 その後、私が用意した、人を模した人型の紙にどんな呪いをかけたいかをその客自身に書いてもらった。
「本当に呪いをかけてもよろしいですね?」
「ええ、もちろん。」 そんなやり取りのあとで客が帰ると、丑三つの時刻を待って、私は黒箱を金庫の中から取り出した。 木で組まれ黒く塗られ、蓋の上面には鴉の文様が金色で描かれている。
この黒箱はとうの昔に陰陽師が所持していたらしく、それがどういう縁か私の遠い祖先が手に入れ、その子から孫、そのまた孫へと今日まで延々と受け継がれている一子相伝の秘密の箱だと父から聞かされていた。なんでも箱を所持していた陰陽師がある陰謀に巻き込まれ、邪念を放つ妖しき物の怪という濡れ衣を着せられ、惨殺されたそうだ。西洋の魔女狩りのようなものだったのだろう。
その時に流された怨念の血がその箱に陰陽師の無念とともに塗りこめられているといういわくつきのもの。これまで何度か使っているが、この黒箱のチカラはとにかくすさまじい。この箱は先祖代々から「呪いの黒箱」と呼ばれている代物だ。一時期人気を呼んだドラマの「デスノート」みたいなものだといえば理解しやすいかもしれない。
私は、客が書いた人型の紙と毛筆をその箱に入れ、蓋をした。紙に書かれた内容は見ないのが私なりのルールなのだが、蓋をする際、ちらりと紙に目をやると、「痛い目に」という文字だけが目に入った。呪いの儀式はこれで完了だ。
それから一か月ほどして、例の客がやって来た。 客はひどくやつれてはいたが、顔を上気させ興奮し、上機嫌だった。 呪いをかけた相手の男は、呪いの儀式を終えた二週間後にゴルフをしに行ったとき、後ろの組にいた人が打ったボールが顔面を直撃し、命は取り止めたものの、左目を失明するという重症を負ったということだった。 人型の紙に書いた呪い通り「痛い目」に遭ったことになる。 客は凄い効き目ですねと感心し、私は「まあ、呪いですから」とだけ答えた。 私は客から謝礼を受け取った。 これで私の仕事は終わった。そのはずだった。だが…。 客は依頼が完了したにもかかわらず一向に帰ろうとしない。
私が「では、これで。」と促すと、それまで沈黙していた客が「実はもう一回お願いしたい。」と言い出した。
「ダメです。それはできません。一回きりというお約束でした。」と返しても、聞く素振りもなくがんとしてそこを動かない。「あと一回。」「これで最後ですから。」「なんとかお願いします。」と繰り返すばかり。 お願い、無理ですの押し問答がしばらく続いた。 そして私はついに折れた。その客にただならぬ憎悪と言うか狂気のオーラが漂っていたからだ。この執念は尋常ではない。
このままでは、本人が自身を追い詰める結果になる。 私は「わかりました。」と答えた。 続いて私は客の額をじっと見つめた。すると見えてきた。 客の恐ろしいほどの憎悪は、今度は自分の奥さんに向けられていた。奥さんはまだ若い。客よりおそらく二回りくらいは違うほど若い。なぜ年の差結婚なんかと思ったが、それは聞くまい。 それから私はもう少し詳しく事情を聞くことにした。 客の話によると、奥さんは自分を裏切って不倫を重ねていたらしい。相手は例の目に大怪我を負った上司だったのだ。あの事故に遭っても不適切な関係は続いている。それどころか事故以来、どういうわけかより親密になっているのだという。
しかも、客である夫に多額の保険金をかけて、あわよくば保険金を狙っているとのこと。いつか殺されるに違いない。その真偽はわからないが、客は少なくともそう信じ切っている。 客が写真を一枚取り出した。奥さんが写っていた。やはり若い。ショートカットの髪型をしていてなかなかの美人だ。この人がそんなことを…。 それから、客は一週間後に毛髪を持ってやってきた。私は黙って受け取る。 その後、客はまた人型の紙に呪いの言葉を記すと帰っていった。呪いの代行をすることがどんな結果をもたらすか、なんとなくわかる。恐ろしいことだ。
だが、これは仕事だと割り切るしかない。決して気持ちのいいものではないのだが。 私は前回同様に、丑三つ時に人型の紙と毛髪を黒い箱に入れ、蓋を閉じた。紙に書かれた内容は、今度はあえて見ないようにして。 あれから三か月たった。客からの連絡は一切ない。呪いの相手はどうなったのかはわからない。前金をもらっていることもあるし、それは私の関知しないことだ。
あれ以来、幸いというか呪いの代行の依頼は来ていない。呪い代行はもういいかとも思う。細々だが占いだけでなんとか食っていける。 例の客のことを忘れかけていたとき、突如としてまたあの客が姿を現した。びしょ濡れの恰好で、前よりもさらに生気を失っている。
「結果はどうでしたか?今日いらしたのはその報告に?」と尋ねても返事がない。客は黙ったままこちらを見つめている。面倒なことはもうたくさんだ。ここは帰ってもらおう。
「今日はもうそろそろ店じまいなんで。」と片づけしながら入口ドアのほうを振り返ると、客の姿は消えていた。 ん?どこへ? 気がつくと占いテーブルに毛髪が二本置かれている。なにかいやな予感がした。 翌日、客を紹介した同僚の名刺を探し出し、電話を入れた。
同僚のF氏はいた。「おお、久しぶりです。」「ですね。」 私は挨拶もそこそこにF氏に客のことを尋ねてみた。すると…。
「実は彼、一週間前に亡くなっちゃたんですよ。」
「ええ?」
「先生のとこ言ったんですか?彼、上司の件で悩んでましたから。」 「まあ。で、亡くなったって、どうして?」
「泥酔して、路上に寝込んでしまって、そのまま凍死ですって。まだ凍死するほどの季節じゃないんですけどね。」
「そうだったんですか…。」
「先生、なんかやっちゃいました?呪いとか(笑)」
「まさか。で、奥さんのほうは?」
「昨日、葬儀だったんですが、意外と元気そうでしたよ。」
「元気…。」
「参列者から聞いたんですけど、なんでも彼に多額の保険が掛けられていたみたいで、この先の生活は安泰みたいで良かったですけど。」
「保険ですか…」
客の言ったことは当たっていた。
「それに、ここだけの話なんですが、もう再婚の話も出ているみたいで。お相手がなんと、彼の上司らしくって。
「上司?」
「亡くなった彼の上司ですよ。前に事故で片方の目を失明したパワハラ上司なんですよ。その上司と再婚話が。」
「…そうでしたか。いや、わかりました。ありがとう。またこんど遊びにきてくださいよ。久しぶりに飲みましょう。」
「そうですね。都合をつけて伺います。仕事と彼女の件で占ってほしいこともありますから。」 「わかりました。お待ちしています。」
「お安く占って(笑)」
「あはは。わかりました。では(笑)」 私は電話を切った。
それにしても、代行した呪いは何だったのか。頭が混乱している。とにかく昨晩姿を現した客が一週間も前に亡くなっているのだ。変だ。あれは霊だったのか…。しかも呪いがまるで効いていない。 私はしまったままにしていた黒箱を金庫から取り出して、蓋を開けた。中に毛髪と人型の紙。 私は改めて紙の文字を見た。
そこには、 「身も凍るような思いをさせてやる」と書かれていた。 身も凍る。客の死因は凍死。…まさか。 私は毛髪を再度じっと観察した。しばらく観察をして、ハッとした。 これは…これは奥さんの毛髪ではない。客の毛髪だ! だから、亡くなってしまったのか…。 なぜ違う毛髪を? 一体、これは…。私はしばらく座り込み考えていた。 考えられる可能性は二つある。
ひとつは自ら死を選ぶことにして、あえて自分の毛髪を持って来たということ。 そして、もうひとつは…。 奥さんのと間違えてついうっかり自分の毛髪を持って来てしまったということ。 どちらなのだろうか。が、いまとなっては知ることができない。 ただ、昨晩、客がやって来たということは。そして悲しげなあの恨めしそうな表情は。 私は思わずテーブルの上を見た。毛髪が二本残されたままになっている。 毛髪くらい風で飛んでしまってもおかしくないのに、しっかりとそこに残ったままになっている。
やがて私はひとつの結論に達した。これは客からのメッセージなのだ。 間違ったにせよ、意図的にせよ、違う毛髪を持って来た客が最後の最後にまた二本の毛髪を置いていったということは、これが最期の呪い代行の依頼なのだと。 だからその二本が誰の毛髪なのかはすぐわかる。 私はその二本の毛髪を使って、作業に取り掛かった。 今回はぬかりなく、念入りに。 やがて、時がたち、F氏と飲む機会を得たときに、彼の口から事の顛末を聞くことができるだろう。 奥さんは電車に飛び込み、上司はビルから飛び降りたという顛末を。
客の依頼はこれでようやく完結する。 さて、あなたも呪いに興味をお持ちですか? もし、お持ちなら・・・私たち呪鬼会の呪術師はあなたの街にもきっといます。 もちろん、秘密の恨み言もお聞きしますよ。ふふふ。
※この作品はフィクションです。実在の人物・団体・事件とは一切関係がありません。