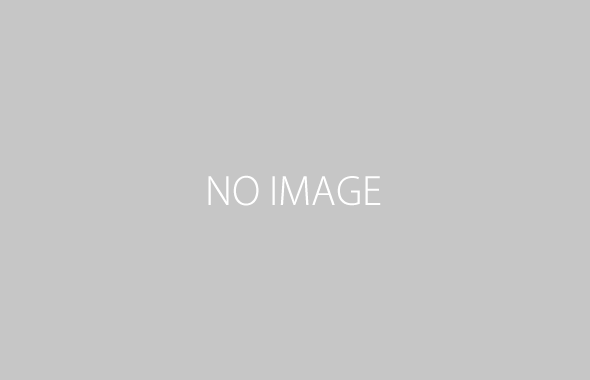呪鬼会監修――日本で実際に起きた呪いの事件【完全解説/保存版】
呪鬼会監修――日本で実際に起きた呪いの事件【完全解説/保存版】
「あなたは、“呪い”を現実のものとして捉えたことがありますか?」
「それは昔話や都市伝説の中の話だと、一笑に付してはいないでしょうか?」
「本日は、“呪い代行 呪鬼会”が監修のもと、日本で実際に起きた“呪い”にまつわる事件の数々を、呪術の視点から解説いたします。」
「これは決してホラー作品の筋書きではなく、現実の社会の中で静かに起こった、そして忘れ去られてはいけない、“呪い”の真実です。」
(音楽:低く、不穏な和風の旋律に切り替わる)
「それでは――、はじめましょう。」
【第一章:祟りの人形――供養されなかった魂の逆襲】
2016年。大阪の某テーマパークで開催された“ハロウィンイベント”にて、実際に供養された日本人形がアトラクション内に使用され、大きな波紋を呼びました。
そのアトラクションの名前は、「祟り-人形の呪い」。
設定は、封印された神社に迷い込んだ来場者が“人形供養を怠った者たちの祟り”に巻き込まれるというもの。
問題視されたのは、実際に神社で供養された人形を使用していたという点。
一部の人形には強い“念”が残されていた可能性が高く、イベント期間中にはスタッフの怪我、システムトラブル、ゲストの転倒など、大小様々な“事故”が多発したと報告されています。
一部の関係者は「因果関係はない」と主張しましたが、呪術の観点から言えば、魂を慰めるべき存在を“見世物”として扱ったことで、霊的干渉を引き起こした可能性は否定できません。
“祟り”とは、無念の想念が“形”をとって現れる現象。 そして、人形という“依り代”は、それに最も適した媒体なのです。
【第二章:コックリさん――自己暗示と霊障の境界線】
こっくりさん。 1970年代以降、日本中の学校で一大ブームを巻き起こした“降霊術”の一種。
紙に50音と「はい・いいえ」を書き、硬貨を指に乗せて「こっくりさん、おいでください」と唱える――。
この一見単純な遊びが、実際には“霊的次元への招請儀式”であることを、多くの人は知りません。
事例1:1970年代、神奈川県の某中学校にて。 部活動中にこっくりさんを行った10名の生徒が、次々と錯乱、泣き出し、幻視・幻聴を訴え、救急搬送される騒ぎとなりました。
事例2:1985年、静岡県。自宅でこっくりさんをしていた主婦が突然錯乱し、救急搬送。
事例3:2013年、兵庫県。女子中学生21人が一斉に過呼吸を起こし、そのうち3人が入院。
呪術的視点では、これは“集合的無意識”の暴走現象と解釈できます。
霊を呼ぶという意図を持ち、複数の人間が“依り代(硬貨)”を通じて念を集中させることで、空間に“歪み”が生じる。
結果、何かしらの“存在”が入り込み、集団的な感応・憑依状態を引き起こしたと見ることもできるのです。
【第三章:白金高輪硫酸事件――呪詛の言葉と意図の暴走】
2021年。東京・白金高輪駅。
駅構内で硫酸をかけられ、大怪我を負った男性A氏。
加害者は、大学時代の知人であるB氏。
この事件の特異点は、“犯行前に呪いの手紙”が送りつけられていたことです。
「あなたに呪いをかけた」「反省すれば解呪のヒントがわかるでしょう」
呪術者の目から見れば、これは“言霊による呪詛”の典型例です。
現代社会では、言葉は“情報”として軽視されがちですが、実際には精神と肉体、空間に影響を及ぼす“力”を持ちます。
恨み・嫉妬・憎しみといった感情を長く抱え続けた者は、その念を“呪い”として外に向けて放つことがあります。
この事件は、呪いが“犯罪”として顕在化する一例であり、人の“念”がどれほど危険な力となり得るかを示しています。
【第四章:自動わら人形事件――言霊と器物損壊の境界】
2017年。東京都江戸川区。
小学校の通学路に位置する歩道橋に、“手作りのわら人形”が吊るされているのが発見されました。
添えられていた紙には、「クソガキどもがここから飛び降りますように」との文字。
さらに周辺では、「ぶち殺す」「アホガキは死ね」などの落書きが30件以上見つかっていたことから、警察は“呪いを用いた脅迫”と判断。
防犯カメラの映像から、41歳の無職男性が逮捕されました。
供述によれば、「子どもの声がうるさかった」というのが動機。
しかし、問題は単なる騒音ストレスに留まりません。
呪術的観点では、“わら人形”は特定対象への“念の転写媒体”であり、公共の場に吊るしたことで多くの人々の潜在意識に干渉する力を持ちます。
その結果、地域全体に“負の気配”が広がった可能性もあると見られています。
【第五章:牛の刻参り事件――法的不能犯と呪術的有罪】
昭和29年。秋田県。
胸の痛みで倒れた女性。どんな治療も効かず、病状は悪化。
その恋人の男性は警察にこう訴えました。
「彼女は呪われている。牛の刻参りで呪いをかけられているんです」
調査の結果、元恋人の女性が夜な夜な神社にて“白装束・藁人形・五寸釘”を用いて牛の刻参りを行っている姿が目撃され、現行犯逮捕。
その直後、呪われていたとされる女性は回復へと向かいます。
これは、呪術の“効力が解けた”ことを意味します。
呪いとは“見えない毒”のようなもの。 発信者と受信者、両者の関係と精神状態により、現実世界にすら干渉しうる――。
その実例なのです。
【第六章:プーチン人形事件――現代における呪いの表現】
2022年。千葉県松戸市。
市内10ヶ所以上の神社の御神木に、ロシア大統領プーチン氏の顔写真が貼られた“藁人形”が打ち付けられているのが発見されました。
逮捕されたのは市内在住の男性。
供述では、「戦争をやめさせたかった」
これは、個人的な怒りや恨みではなく、“世界に対する抗議の儀式”としての呪術の形式でした。
しかし問題は、“神社の御神木”を使用した点。
呪術は意図と対象、そして“場所”に大きく影響を受けます。
御神木は神霊が宿る神聖な依り代。 そこに呪術をぶつけたことで、神社にとっては“穢れの侵入”と捉えられる行為であり、器物損壊の罪に問われたのです。
【第七章:呪いとは何か――精神と現実のはざま】
これまで紹介してきた事件の数々は、決して“偶然”や“迷信”では片づけられない事例ばかりです。
“呪い”とは、人の心が生み出したもう一つの現実。 そしてその力は、時に人を傷つけ、命を奪い、社会に影響を与えるほどに増幅することがあります。
逆に言えば、“祈り”や“赦し”といった意識の方向性によって、その力を“浄化”や“癒し”に変えることも可能です。
呪術とは、“心を操る術”であり、
だからこそ、その扱いには深い知識と倫理、そして技術が求められるのです。
【エンディングナレーション】 (笛の音が静かに響く)
「私たち“呪い代行 呪鬼会”は、 30年以上にわたり、日本国内外から数多くの相談を受け、 その想念と向き合い、解決へと導いてきた専門集団です。」
「私たちの使命は、“恨み”や“憎しみ”という負の感情を、 正しい形で昇華させ、現実の解決へとつなげていくこと。」
「もし、あなたが今、心に深い苦しみや怒りを抱えているのなら――。 どうか、一人で抱え込まず、私たちにご相談ください。」
「公式サイトでは、無料相談・匿名相談も受け付けております。」
「“呪い”とは、ただの脅しではありません。 それは“想い”であり、“力”であり、“意志”の結晶です。」
「その力を正しく扱い、あなたの人生を取り戻すために――。 呪鬼会は、いつでもそばにおります。」